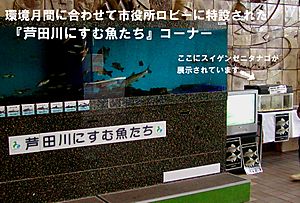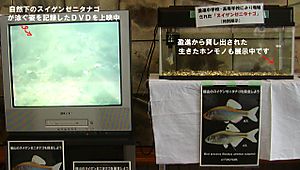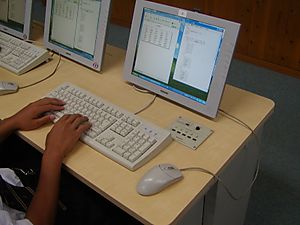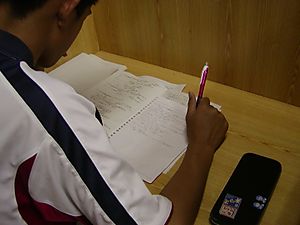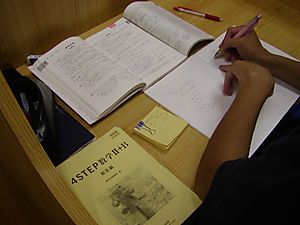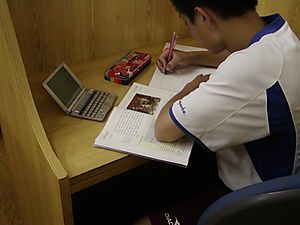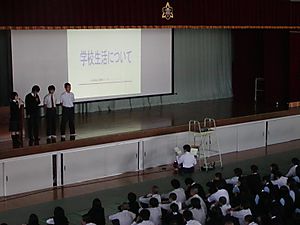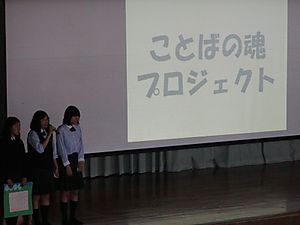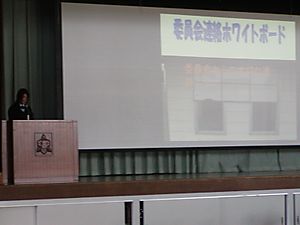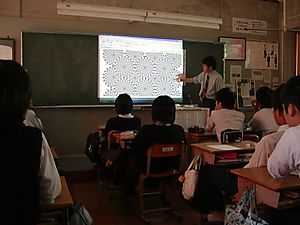第一回研究授業(授業参観)週間 LAST
第一回研究授業(授業参観)週間は今日で終わりです。本日も授業の様子をレポートします。
4年B組の家庭基礎の授業です。生徒たちは先生をお手本にしながらエプロンを作成中です。普段裁縫をしない生徒にとっては、一つひとつの作業を難しいと感じているようです。
5年C組の生物の授業です。顕微鏡を利用して、微生物の観察をしていました。慣れない作業に手間取りながらも、生徒たちは楽しそうに顕微鏡をのぞいています。
6月11日(金)には、塾の先生方を対象に、2010年度第1回公開授業を行います。テーマは『思考を鍛える授業づくり~楽しく元気に~』『1クラス単純2分割少人数授業~仲間と共に~』で、英語と数学で行います。
また、研究授業(授業参観)週間は、第二回を9月13日(月)から17日(金)、第三回を11月15日(月)から19日(金)に行います。第二回の研究授業(授業参観)週間には、塾や公立中学校の先生方対象の公開授業を予定しております。
これからも、授業内容の充実を目指し、教員は努力を続けていきます。